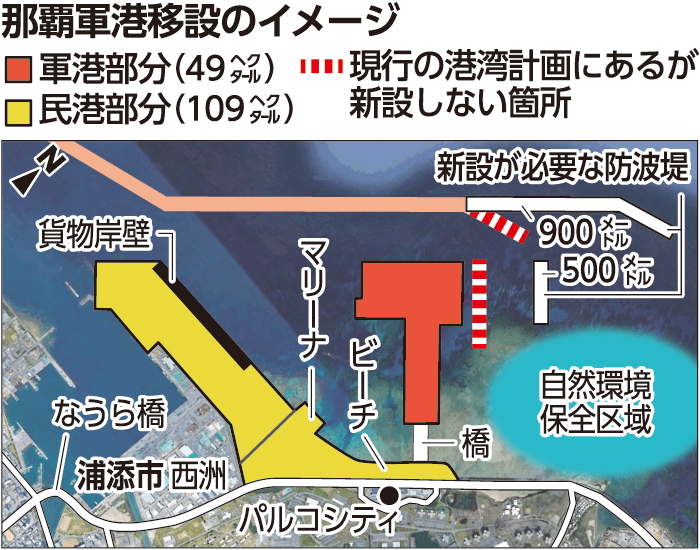2024年、米不足から店頭から米が消えるといった事態になり、価格も異様に上がった日本。新米が出れば安定するのではとの見方もあったが、11月22日現在、米の価格は依然高いままである。経営に苦しむ飲食店、家計への影響などが今も報じられている。この状況に、私はある疑問を抱いている。
疑問を抱く理由として先ず挙げられるのは、「2024年のコメの生産量は前年より22万トン多い683万トンと、24年7月〜25年6月の需要見通しの674万トンを上回ると予測」①されていることだ。引用は10月30日付けの日本経済新聞の記事『24年のコメ、需要上回る生産 来夏の不足なお懸念』からである。同記事には農水省の分析として、「今夏のコメ品薄は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を受けた買い込みが主因」②であり、新型コロナウイルス禍から回復したインバウンド需要の急激な伸び(14万トン)も原因であり、来年また海外からの観光客が増加すれば需要が大きく減るかは不透明であるとしている。
昨年よりも生産量が増えているが、海外からの観光客が増え需要が高まれば再び米の供給は不安定になるという。観光客がそれほどの米を消費するのだろうか?14万トンという数字は正確なのだろうか?そのような疑問を抱いたのである。
その一方、「ことし(2024年)1月から7月の日本のコメの輸出量は2万4469トンで去年の同じ時期より23%増え」③ている。同時期の輸出額は64億6200万円で、前年比で3割上回るペースで、年間では初の100億円に到達する可能性もあるという。
輸出量のトン数は大したことのないように見えるが、気になるのは輸出額である。1トンあたりにすると26万4千円である。日本国内の流通では23万円であることを考えると、国内で流通させるより海外に売った方が儲かってしまう。海外に売る業者が増えるのではないか?それが私が抱く懸念である。
この懸念を抱くのにも理由がある。私は仕事で海外から農産物を仕入れることがあるのだが、輸入価格はコロナ禍前の倍以上になっている。こうした輸入品の価格高騰は、コロナ禍後の急激な流通再開、円安などが原因であるとされていた。しかし、海外の業者と価格について相談したときこう言われたことがある。
「なぜ日本にだけ安く売らないといけないのか」
他所の国の仕入れ業者と同じ値段で買え、というのである。その時、私の頭をよぎったのは、この30年、日本国民の平均所得が上がっていないことである。欧米やオセアニア、それにアジアの中には既に日本の所得を大きく上回るほど経済成長をしている国が多く存在する。そのような国に旅行に行けば、物価は倍以上であることを実感する。観光地価格であること、円安を理由にしてみても、どうもそれだけが原因とは思えないほど高い。国内の所得が上がり経済成長している国では物価は上がる。停滞している日本だけが、取り残されているように思えてならない。
日本の場合、国内で生産されたものであっても、その原料は輸入に頼るものが多い。畜産にしても、飼料は輸入品が大半を占めるであろう。海外との差が開けば、日本国内全体で、あらゆる商品の物価は上がり続ける。海外アーティストの公演チケットのようなものも、向こうの感覚で値がつけられるとしたらやはり高額になっていくのだろう。そして日本国内よりも海外の方が高く買うから…という理由で輸出が増えるのであれば、日本は益々貧しくなっていく。さらに言えば、輸出をしている業者が、国内だけ安く売るということも考えにくい。
以上は、私自身が抱く懸念であり、社会情勢を正しく分析しているものとは言い難いかもしれない。しかし日本の所得が上がらないことを要因とする物価高騰は確かに存在する…そう言えないだろうか。この懸念を晴らすには、国内生産の地力を増やす政策、そして所得を上げる地道な努力しかないように思う。30年の停滞はあまりにも大きいが、今すぐにとりかからないと、円は紙切れ以下になってしまうのではないか。そうした不安が頭をよぎる。
[引用]
①、②日本経済新聞「24年のコメ、需要上回る生産 来夏の不足なお懸念」2024年10月30日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA294O90Z21C24A0000000/#:~:text=%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%81%AF30,%E3%82%92%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%82%8B%E3%81%A8%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82(2024年11月23日閲覧)
③NHK首都圏ナビ「コメ不足2024 生産量や輸出は?ふるさと納税の返礼品の在庫 茨城県八千代町などでは」2024年9月4日
https://www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/011/29/#:~:text=%E3%82%B3%E3%83%A1%E8%BC%B8%E5%87%BA%E9%87%8F1%EF%BD%9E,%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82(2024年11月23日閲覧)