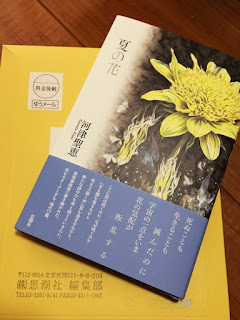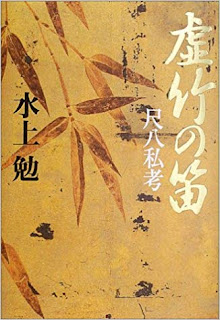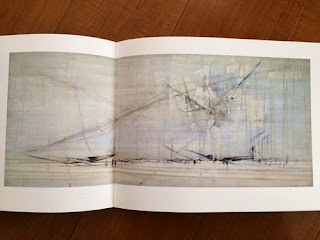何年か前、4月下旬から5月にかけて、青森へ行ってきました。
弘前の桜まつりを見ることなどいくつか目的があったのですが、その中に「桜が咲く頃の青森市を歩くこと」がありました。
青森出身の詩人、寺山修司の記憶を辿り、寺山にとっての「五月」と「青森の桜」を感じてみたかったのです。
私が好きな詩人、寺山修司は、昭和10年12月に弘前で生まれました。
幼少時の寺山は八戸、三沢など青森県内を転々としていますが、昭和23年に大叔父が経営する青森市の映画館に引き取られます。
この映画館のあった場所は青柳2丁目で、現在はモルトン迎賓館という結婚式場になっています。
その3年後、青森高校に入学した寺山は青森市松原に下宿します。
青柳と松原は歩いて行けるほどの距離です。
青森高校を卒業した後、寺山は上京しますから、青森で最も長い時間を、それも13歳から18歳の最も多感な時期を過ごしたのが青森市青柳と松原、つまり堤川沿いの地域となります。
そしてこの地域の地名が登場する詩に「懐かしのわが家」があります。
肝硬変で亡くなる前年の昭和57年に発表され、遺稿とされている作品です。
短い詩なので、全文を紹介します。
昭和十年十二月十日に
ぼくは不完全な死体として生まれ
何十年かかゝって
完全な死体となるのである
そのときが来たら
ぼくは思いあたるだろう
青森市浦町字橋本の
小さな陽あたりのいゝ家の庭で
外に向って育ちすぎた桜の木が
内部から成長をはじめるときが来たことを
子供の頃、ぼくは
汽車の口真似が上手かった
ぼくは
世界の涯てが
自分自身の夢のなかにしかないことを
知っていたのだ
作中に出てくる浦町字橋本は、寺山が暮らしていた青柳と松原から近い場所です。
ただ、現在の浦町字橋本は公園の一部のみを指すようで、陽当りのいい家も、大きな桜も見当たりませんでした。
ですが、死期を悟っていたであろう寺山が、最後に思いあたるであろう光景は、青森市の桜だったことに間違いありません。
青森市の中心街、橋本に近い宿に滞在して、私は市街地を歩きました。
枝垂桜、ソメイヨシノなど、街ではあらゆる桜が一斉に咲いていました。
咲き方も見事で、同じソメイヨシノでも青森の桜は堂々と咲き誇っているように見えました。
大きな桜が多いのです。
それはまさに、「外に向かって育ちすぎた桜の木」そのものでした。
寺山修司は、5月を題材にした作品が多いことでも知られています。
5月の青森の桜を眺めながら、私は寺山にとっての「五月」を想像しました。
寺山の第一詩集「われに五月を」は、1957年に刊行されましたから、22歳よりも前に書かれたものであることは間違いありません。
この詩集に収めらている「五月の詩」にはこうあります。
二十才 僕は五月に誕生した
僕は木の葉をふみ若い樹木たちをよんでみる
いまこそ時 僕は僕の季節の入口で
はにかみながら鳥たちへ
手をあげてみる
二十才 僕は五月に誕生した
12月生まれの寺山ですが、5月こそが彼の季節であったことがわかります。
「五月に誕生した」ならば、その場所はどこになるのだろうか?
寺山は、どこの5月を思い浮かべて、この詩を書いたのだろうか?
「二十才」のころ、寺山は早稲田大学に入学し東京で生活をしていたものの、ネフローゼで立川の病院に長期入院をしています。
「二十才」で入院したことを「誕生」とし、闘病中に執筆したのであれば東京である可能性は高く、私自身も自分が育った東京の5月を思い浮かべながらこの詩を読んできました。
しかし青森の桜を前にすると、青森市なのではないのかとも思えてくるのです。
20歳で書いたかもしれないけれど、思い浮かべていた5月は青森の風景だったのではないか。
一斉に咲き誇っていた青森の桜は、こどもの日を過ぎる頃、あっという間に葉桜になります。
「木の葉をふみ若い樹木たちをよんでみる」
既に新緑の5月の東京よりも、青森の風景の方があてはまるように思えてならないのでした。
ところで、「懐かしのわが家」の途中(「内部から成長をはじめるときが来たことを」の後)に、「五月の詩」の紹介した部分を続けると、あまり違和感なく読めてしまうのではないでしょうか?
昭和58年5月4日、青森では桜吹雪が舞う「五月」、寺山修司は47歳でこの世を去ります。
寺山にとって死は、自身の「季節の入り口」をくぐることに他ならなかった。
私はそう思いたいのです。
(追記)
青森市に滞在した後、私は弘前へ足を伸ばしました。
寺山が生まれた街です。
弘前城の桜は、昼も夜も見事なものでした。
これほど綺麗な桜を見たのは初めてです。