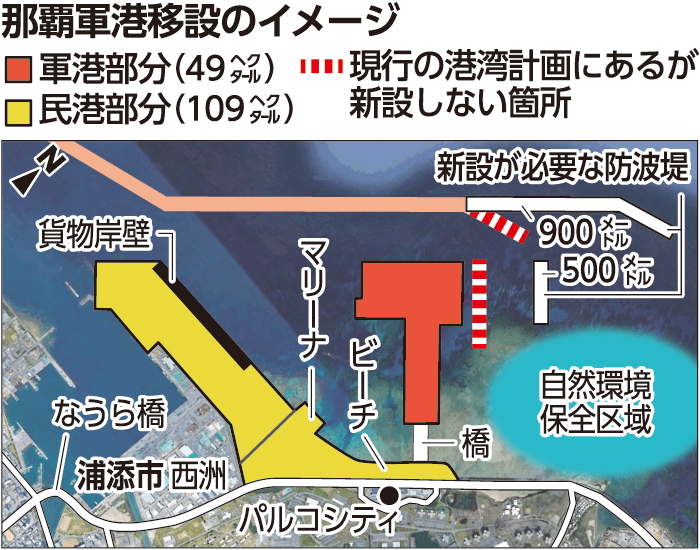ベヴァリッジ報告の内容と日本の社会保障制度が受けた影響について整理し、その原点に立返る必要性について以下述べる。
ベヴァリッジ報告は、1942年にイギリスの経済学者ベヴァリッジが発表した社会保障制度改革のための報告書である。その目的は戦後のイギリス社会の再建と福祉国家の実現であった。ベヴァリッジは、イギリスが克服すべき社会的問題を、欠乏、疾病、無知、不潔、怠惰の五大巨悪とし、それらに対抗するためには国家による社会保険制度の整備が必要であると主張した。
ベヴァリッジ報告の主な内容は以下のとおりである。
①社会的リスクに対して、国民全体が参加する社会保険制度を整備すること。社会保険には、健康保険、失業給付、年金などが含まれる。社会保険は、労働者と雇用者、そして国家が拠出する保険料によって賄われる。
②社会保険制度によって最低限度の生活保障(ナショナル・ミニマム)を確保すること。ナショナル・ミニマムとはウェッブ夫妻が提唱した概念で、人間らしい生活を送るために必要な最低限の所得やサービスの水準を指す。
③社会保険制度に加え、特別な事情によって生活困窮に陥った人々に対し、国民扶助という公的扶助制度を設けること。国民扶助は資力調査(ミーンズテスト)を条件として、補助金や物品の提供などの形で行われる。
④ナショナル・ミニマムを超えるサービスを望む人々に対し、任意保険を認めること。任意保険は自由主義経済の原則に基づき、個人の選択と責任に委ねられる。
⑤社会保障制度の実施には次の三つの前提条件を満たすこと。
ⅰ)児童手当の支給。大家族の所得保障、子どもの健全な生活の確保。人口維持のために全ての子どもに対し児童手当を支給。
ⅱ)包括的な保険およびリハビリテーション・サービスの提供。病気の予防や治療、リハビリテーションを全ての国民に保障するため国民保健サービスを創設。
ⅲ)雇用の維持。失業者の大量発生を防ぐため、完全雇用政策を実施。
以上がベヴァリッジ報告の概要である。
ベヴァリッジ報告はイギリス国民の関心を集め、戦後の福祉国家への期待が高まっていく。1945年に誕生したアトリー政権は、ベヴァリッジ報告を基に、1946年の国民保険法、1948年の国民保健サービス法や国民扶助法などを制定し、いわゆる「ゆりかごから墓場まで」の福祉国家を実現したのである。
社会保障制度の主要手段として社会保険を位置づけたベヴァリッジ報告は、世界各国にも影響を与えた。日本でも日本国憲法の制定により社会保障に対する国の責務が規定され、1950年には社会保障制度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を発表、社会保険を中核に社会保障制度を構築すべきとした。
日本の社会保障制度は、ベヴァリッジ報告が社会保障計画の構成として示した、社会保険、国民扶助、任意保険という三つの方法を基本とし発展していく。1961年には地域保険である国民健康保険、国民年金に農家や自営業者などを加入させることで国民皆保険・皆年金が実現した。
そして、ベヴァリッジ報告にある三つの前提、「完全雇用」「所得制限なしの児童手当」「包括的な保健サービスの提供」に基づいて日本でも制度改革が進められた。1971年に児童手当法が制定、1973年の「福祉元年」には、老人医療費の無料化や、医療保険における高額療養費制度や年金の物価スライド制などが導入されたのである。
前述のとおり、ベヴァリッジは社会保障制度の敵として五大巨悪を挙げた。これは、社会保障制度は貧困や疾病などの結果に対処するだけではなく、その原因にも取組むべきであるというメッセージであると言えよう。今、日本の社会保障は財政的に持続可能かが大きな課題となっている。ベヴァリッジ報告の原点に立返り、巨悪は何か、その原因を検証し解決していく姿勢こそが必要ではないかと考える次第である。
[参考文献]
・ウィリアム・べヴァリッジ(著)『べヴァリッジ報告 社会保障および関連サービス』法律文化社 2014年