人生で経験する事象のすべてを自身の思考で整理することは、恐らく不可能でしょう。他人の言葉を己の思考の出発点、或いは知の糧とすることは、思考を先へ進めるために非常に有効であると考えます。また、そうした言葉は私を構成する一部となっています。このページでは私自身のノートを兼ねて五十音順にまとめていきます。
※昔ノートに書き留めた際、版元を記入していなかったため、出典が不明のものもあります。
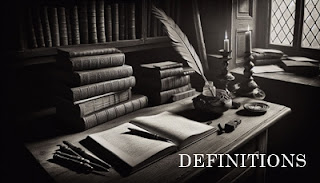.jpeg)
愛
愛はだまって表現するしかない行為で、言葉ではない
水上勉『生きるということ』講談社 (講談社現代新書)1972年 P67
「愛」の字を使う時は、よほどの勇気がいるのである。「真実」ということばも、そういえばめったにつかわない。(中略)愛や真実という言葉が、それほど、かんたんにつかえる人間なら、小説を書く必要はない
水上勉『生きるということ』講談社 (講談社現代新書)1972年 P64
言ってしまう、愛することこそ人間が避けることができない放浪である
東由多加『東由多加が遺した言葉』而立書房 2002年 P46
愛は能動である
エーリッヒ・フロム『愛するということ』紀伊國屋書店 2020年 P190
アイデンティティ
アイデンティティという言葉には、〈職業〉という社会構造上の属性はもちろん、〈正直〉というような人柄を表す属性も同時に含まれている
アーヴィング・ゴッフマン『スティグマの社会学』せりか書房 2001年改訂版 P14
アイロニー(イロニー)
水田君に贈る 一七年(一九四二)一月二一日
ただイロニイを解する者だけが現代を知る、ということができる。だから私はロマンティストならざるロマンティストを愛するのだ
高島善哉 「水田洋著『アダム・スミス論集』」ミネルヴァ書房 2009年 P497
悪
世界の悪は おたがいに気にすること
良かれとか悪しかれと思ったりすることに由来する
フェルナンド・ペソア『ペソア詩集』思潮社 2024年改版 P45
アプリオリ
〈先験性(ア・プリオリ)〉とは、決して言われないことも、現実的に経験に与えられないことも、ありうるような心理の先験性ではなく、与えられた一つの歴史である
ミシェル・フーコー『知の考古学』河出書房新社 1996年改訳版 P196
アメリカ
目はどこにある、見る意志のある目は
慈悲に溢れた心はどこにある
俺を見捨てなかった愛はどこにある
俺の手、俺の魂を解放してくれる仕事はどこにある
俺の心を支配する精神はどこにある
アメリカの夢の約束は
今この国のどこにある
ブルース・スプリングスティーン『We Take Care Of Our Own』
怒り
愛憎は人間と人間とのあいだにしか生れぬ感情だが、怒りはときとして神に向かっても向けられる。それは、自然と人間とのむなしい闘いのなかにも生れる、きびしい情念の父なのである
寺山修司『街に戦場あり』筑摩書房(ちくま学芸文庫)2025年 P160
生きる
たとえ無価値と人はいおうとも、生きるには、無意味に手をふる必要があるのである
水上勉『心筋梗塞の前後』文藝春秋(文春文庫)1997年 P220
生きる意味を問うのではない。また、生きることが幸福を約束するものでは必ずしもない。生きる意味はどうでもいいから、生きることに挑戦して身を投げ出すことのなかに(結果は幸せもあろうし挫折もあろうが)、その行為のなかにこそ人が生きた証があるのだ
蟻塚亮二『3・11と心の災害』大月書店 2016年 P211
意志
意志とは、運命に対する権力の証言であり、偶然的なるものの排除である
C・G・ユング『無意識の心理』(新装版)人文書院 2017年 P81
意識
意識はそれ自身も流動する数限りない心象が映っている流動する鏡である
ジョルジュ・プーレ『人間的時間の研究』筑摩書房 1969年
意識は単に脳の活動の副産物でしかなく、人間が死ぬ時、生物学的過程が終わるだけではなく、すべての意識も途絶える
ジョージ・A・ボナーノ『リジリエンス』金剛出版 2013年 P153
逸脱
社会集団は、これを犯せば逸脱となるというような規則をもうけ、それを特定の人びとに適用し、彼らにアウトサイダーのラベルを貼ることによって、逸脱を生みだすのである。この観点からすれば、逸脱とは人間の行為の性質ではなくて、むしろ、他者によってこの規則と制裁とが「違反者」に適用された結果なのである
ハワード S ベッカー『アウトサイダーズ』現代人分社 2019年POD版 P8
イデオロギー
イデオロギーとは、利害関係に染まってはいるが、それなりに正当な根拠をもった幻想である
ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオンⅠ』藤原書店 2020年(普及版) P132
イデオロギーというものは自ら考え、自ら行動することのできない他人志向型の人間の覚醒剤である
高島善哉『時代に挑む社会科学』岩波書店 1986年 P19
イデオロギーを論じあってみたところで、何になるだろう?すべては、立証しうるかもしれないが、またすべては反証しうるのだ。しかもこの種の論争は、人間の幸福を絶望に導くだけだ。それに人間は、いたるところぼくらの周囲で、同じ欲求を見せているのだ
サン=テグジュペリ『人間の土地』新潮社(新潮文庫)1998年改版 P220
命
命がけとは自分を安売りしないこと
谷川雁『原点が存在する』弘文堂 1958年
「命をかけて患者さんを守った」という評価には反対だ。生きることの価値以上に、この世に絶対的な価値は存在しない。だから「命をかけて〇〇する」というのはすべて虚偽である。命は何事にもかけてはならない
蟻塚亮二『3・11と心の災害』大月書店 2016年 P61
意味
ただひとつのの「意味」は
わたしたちが注ぐ集中力、注意力から生じる。
おそらくそれで十分なのだ、なぜなら、
そのなかのどこかで、わたしたちは自分の「フロー」を見つけるのだから
リジー・ホーカー『人生を走る』草思社 2021年 P159
医療
医療の枠組みや手順がうまく機能していなければ、医師は一歩引いて、症状が語る話を傾聴しなければならない。最善の解決方法は、医師と患者が共通の認識基盤を築けたときに見出せるものなのだ。(中略)この認識基準を見出すことを可能にするコミュニティに属している場合、回復の最善の機会が得られる(中略)そのようなコミュニティの条件とは、「偏見を持たずに患者の話に耳を傾ける」「支援を提供できる」「利害を脇に置いて謙虚さを保ち、不完全さや失敗に寛容である」「健康に関して全体的な視野を持つ」ことだ(中略)いま私たちがすべきことは、このようなコミュニティの構築なのだ
スザンヌ・オサリバン『眠り続ける少女たち』紀伊國屋書店 2023年 P420
因果関係
因果関係は、本質的に知覚を通しては推定できない。因果関係の推定はあくまで理論に基づくのである。それゆえ、絶えず補足して考え、事実を仮定し、信じることが必要となる
ウルリッヒ・ベック『危険社会』法政大学出版局 1998年 P37
飢え
われわれにとって、飢えとは、ただ飢えであることは決してない。飢えは記憶、悩ましい喪失の未来である。それは、飢えとはひとつの実存であり、何よりもわれわれの物質的な存在の事実にかかわるものだというもう一面の絶対の極を含んで、われわれの飢えについての真実なのだ
黒田喜夫『燃えるキリン 黒田喜夫詩文撰』共和国 2015年 P259
人はみな我が飢を知りて人の飢を知らず
沢庵『玲瓏日記』
うつ病
「思考と行動」という二つの次元でうつ病を考えると、うつ病は「過度の思考依存であり、頭でっかちで、考えることですべてが解決するかのような錯覚に陥っている」と言ってもいい
蟻塚亮二『うつ病を体験した精神科医の処方せん』大槻書店 2005年 P73
運命
運命は自由意志の中にある
芥川龍之介『「Lies in Scarlet」の言』全集第十二巻 岩波書店 1978年
運命とはある存在がつくり出した虚構である
アラン『定義集』岩波書店(岩波文庫) 2003年 P64
運命とは何である。時計の針の進行が即ち運命である
幸田露伴『努力論』岩波書店(岩波文庫)2001年
エゴイズム
エゴイズムとは、感覚における遠近法の法則である。最も近くにあるものが大きく重要に見え、遠方になるに従って、物事から大きさと重要さが減っていくという法則である
フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』河出書房新社(河出文庫) 2012年 P243
オートマティズム
オートマティズムは――結論的にいえば、芸術創造の原理であることにおいて、人間存在の根本条件にふれて、われわれの心底にあるものをすべて表している
瀬木慎一『創造の美学』合同出版 1965年 P66
音楽
人間は詩によって善の心がふるいたち、礼によって安定し、音楽によって完成する
孔子『論語』筑摩書房(ちくま文庫)2016年 P163
絵画
絵画はしょせん光の言葉にほかならない
アポリネール『アポリネール詩集』新潮社(新潮文庫) 1954年
階級
階級は歴史的な不平等の一形態にすぎず、国民国家はその歴史的な枠組みにすぎない
ジグムント・バウマン『コラテラル・ダメージ』青土社 2011年 P39
介護
「医療」というのは、まず、その方の怪我とか病気などを治すという役割をもっています。でも「介護」の役割はそうではない。生活を生き生きとさせる、生活の自立を促し、その方が自己実践することを促す、その人らしい人生を全うするよう支援するということです
一番ケ瀬康子『生活福祉の成立』明光社 1998年 P201
革命
革命とは運動にほかならないが、運動は革命ではないのだ。政治は変速機にすぎず、革命はその酷使にすぎない
ポール・ヴィリリオ『速度と政治』平凡社(平凡社ライブラリー) 2001年 P30
政治的抑圧と不正に対してなら革命は武器となる。しかし、経済的欠乏に苦しむ人々に、革命がどんな希望の方針をもたらせられるだろう
ジョン・メイナード・ケインズ『平和の経済的帰結』東洋経済新聞社 2024年 P235
要するに、革命というものは、条件の大きな変化によるものである。それ〔革命〕は新しいモーレスを要求する。この刷新がこういった要求に合致するかぎり、その刷新は永久的なものとなり、革命の恩恵であるという確信を助長する
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P113
過去
過去とは時間をかたちづくっている実質である
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『不死の人』白水社 1996年 P201
悲しみ
悲しむことは、他人や自分への信頼感、つまり「生きる」ことに対する肯定的な意思と密接に結び付いた体験だと言える
蟻塚亮二『悲しむことは生きること』風媒社 2023年 P276
神
神なんて苦悩の度合いをはかる観念にすぎない
ジョン・レノン『God』
感情
感情は事実である
F・P・バイステック『ケースワークの原則』誠信書房 2006年 P69
観点
観点というものは、すべて、偽造である
ポール・ヴァレリー『精神の危機』岩波書店(岩波文庫)2010年 P20
観念
《観念》はわたしにとって変形の手段である――したがって、何らかの変化の部分ないし瞬間である。
人間の個別の《観念》は、《それぞれある疑問を変形する手段である》
ポール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』岩波書店(岩波文庫)2004年 P149
記憶
(集団的記憶)
究極的にはフィクションである。厳密にいうなら、集団的記憶というようなものはない。集団的記憶は集団的罪と同様に、一連の虚偽の概念を構成している。だが集団的教訓は存在する。/あらゆる記憶は個人的なもので複製不可能であり、個人とともに死ぬ。集団的記憶と呼ばれるものは、記憶することではなく規定することである。これが大事なのだ、それはこういうふうにして起こったのだ、というふうに。そして記憶をわれわれの心に閉じ込める写真を添付する
スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』みすず書房 2003年 P84
危機
あらゆる危機は、過去の動的ないしは静的均衡を破る、新しい《原因》の介入を意味する
ポール・ヴァレリー 「知性について」『精神の危機』岩波書店(岩波文庫)2010年 P82
危機という名の鳥は、政治的、経済的状態のうちにではなく、人間の魂のうちにのみ見出される
寺山修司『あゝ、荒野』KADOKAWA(角川文庫) 2009年 P200
危険
危険というのは、自分たちが平和な世界にいると思っているときだけ、異常に見える
ジョン・ブライリー『遠い夜明け』 早川書房(ハヤカワ文庫) 1988年 P238
危険とは、歴史の産物であり、人間の行動や不作為を反映したものであり、高度に発達した生産力の表れである。このため、危険社会においては、社会の生活基盤を人間が内部からつくり出したことから、問題や課題が発生する
ウルリッヒ・ベック『危険社会』法政大学出版局 1998年 P376
危険は、人間が歴史的に獲得した能力から発生するのである。つまり、地上の生命体の再生産の基盤を人間が勝手に変えたり、つくり上げたり、破壊することができるようになったことから発生するのである。言い換えれば、危険の根源は無知にあるのではなく知識にある
ウルリッヒ・ベック『危険社会』法政大学出版局 1998年 P376
危険というものは、わたしたちの意識とは独立して「それ自体」として存在するようなものではまったくないのです。危険というものは、むしろ一般的な意識化によって初めて政治的なものになり、科学的な議論のための資料によって戦略的に規定されたり、隠されたり、演出されたりする社会的な構築物なのです
ウルリッヒ・ベック『世界リスク社会論』筑摩書房(ちくま学芸文庫) 2010年 P79
奇跡
奇跡とは、物質主義者の考える物質主義的脱出法にほかならない
グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』思索社 1982年
最大の奇蹟は言語である
芥川龍之介『「Lies in Scarlet」の言』全集第十二巻 岩波書店 1978年
規則
よい規則というのは、最適な時機に本質を思い出させてこれを強制する規則のことであり、もともとその特別の時機の分析から生じたものなのだ
ポール・ヴァレリー『文学論』角川書店(角川文庫)1969年改版 P23
希望
人類が最後にかかる、一番重い病気は「希望」という病気です
寺山修司『あゝ、荒野』KADOKAWA(角川文庫) 2009年 P195
希望とは精神が下す厳密な予測に対する存在者の抱く不信感にほかならない
ポール・ヴァレリー『精神の危機』岩波書店(岩波文庫) 2010年 P12
希望は未来の栄光を疑念をはさまずに待つこと
ダンテ・アリギエーリ『神曲』河出書房新社
絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じだ
魯迅『「野草」全釈』平凡社 1991年 P76
教育
あらゆる教育は、まさに自由と称されるものに帰着する
ノヴァーリス『青い花』岩波書店(岩波文庫)1989年
共感
共感は自己意識と他人意識との本式の区別ではなく、むしろ自己と他人との未分化を前提とするもの(中略)共感とは、わたしが他人の表情の中で生き、また他人がわたしの表情の中で生きているように思うという、その単純な事実のこと
モーリス・メルロ=ポンティ『眼と精神』みすず書房 1966年 P177
われわれ自身の利害や友人の利害にかかわりない社会的善福は、ただ共感によってのみ快感を与える。したがって共感こそ、あらゆる人為的な徳にたいしてわれわれが払う敬意の源泉である道理になる
デイヴィッド・ヒューム『人生論(四)』岩波書店(岩波文庫) 1952年 P188
狂気
狂気は人間の条件の一つです。私たちのなかには狂気が存在しています。理性が存在するのと同じように、狂気も存在しています。文明社会というためには、社会が理性と同じく狂気も受け容れなければならないのです
フランコ・バザーリア『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』岩波書店 2017年 P54
供犠
供犠はある一つの物=客体を従属関係へと縛りつける現実的な絆を破壊する。つまり生贄を有用性の世界から引きはがして、知的な理解を絶するような気まぐれの世界へと戻すのである
ジョルジュ・バタイユ『宗教の理論』筑摩書房(ちくま学芸文庫) 2002年 P55
強制
いったい強制によって人類を道徳的にすることができるものであろうか。征服者と被征服者の攻撃欲動や苦痛欲動は、きまって悲劇をもたらす強制となり、それによる交互作用として、たがいに刺激し合う結果を生じるのではないだろうか。すなわちこれらの欲動は、人類が内に蔵するもっとも危険な欲動であり、ことにこれらが高揚された道徳とか、社会的宗教的幸福とかの衣をまとうとき、つねにいっそう危険の度を増すのではなかろうか
エルンスト・クレッチマー『天才の心理学』岩波書店(岩波文庫)1982年 P63
教養
教養とは単に物を知ることではなく、自己の人間を形成することである。
しかるに自己はただ世界の中においてのみ形成されることができ、人間の自己形成はただ世界形成を通じてのみ達せられることができる。しかも世界を形成するためには世界に関する科学を獲得することが必要である
三木清『戦期間時事論集』中央公論新社(中公文庫)2022年 P104
儀礼
儀礼とは、人が聖物に対してどのように振舞うべきかを規定した行為の基準である
エミール・デュルケム『宗教生活の原初形態(上)』岩波書店 (岩波文庫)1975年 P77
空間
空間は時間を凝縮している。それが空間の役目なのだ
ガストン・バシュラール『空間の詩学』 思潮社 1969年 P43
経験
経験なんて、邪魔以外の何ものでもない
キース・リチャーズ『ローリング・ストーンズ 魔性の美学』シンコーミュージック 1986年 P253
警句
警句とはその時代にちやほやされている考えにあてはまった、修辞上の美辞麗句である。(中略)多くのばあい、警句はただ架空の一般論に形をあたえるだけである
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P234
芸術
芸術はすべて識別であり選択である
ヘンリー・ジェイムズ『The Novels and Tales of Henry James(序文)』
「希望」と「思い出」には一人の娘がいるが、その名は「芸術」である。彼女は人生のすさまじい戦場の戦いの旗として、人間がお互いの衣類を掛ける枝から、遠ざかった場所に住家を造っている
W・B・イエイツ『ケルトの薄明』筑摩書房(ちくま文庫) 1993年 P13
芸術は差異が連続して進む行列だ
トリスタン・ツァラ『ムッシュー・アンチピリンの宣言』光文社(光文社古典新訳文庫) 2010年 P125
芸術の目的。空間と時間をわれわれに感知させる。われわれのために人為的な任意の空間と時間をつくりだす。にもかかわらず、それは時間そのもの、空間そのものである
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』岩波書店(岩波文庫)2017年 P256
芸術家
自己を模倣すること。
芸術家にとって、自己模倣ができるということはきわめて重要だ。
これが作品を築き上げる唯一の手段だ、――なぜかというに、作品は必然的に精神、気力、気分の変化や動揺に対抗してなされるのだから。
芸術家は、自分の最上の状態をモデルとする。彼らが自ら判断して最上のできばえだと思うものが彼の単位として役立つ
ポール・ヴァレリー『文学論』角川書店 (角川文庫)1969年改版 P65
劇場
劇場とは、施設や建物のことではなく、劇的出会いが生成されるための「場」のイデオロギーのことである
寺山修司『迷路と死海』白水社 1993年 P118
欠乏
欠乏は、それを防止する対策をとらないために生じる、起こさなくても良い不面目なのである
ウィリアム・ベヴァリッジ『ベヴァリッジ報告』法律文化社 2014年 P260
欠乏の根絶は単に生産の増大によってだけではなく、生産物の正しい分配を意図的に行うことがなければ達成できない
ウィリアム・ベヴァリッジ『ベヴァリッジ報告』法律文化社 2014年 P263
現在
現在とは二つの永遠に続く連続の間のたんなる一点であり、現在だけという研究対象などありはしない
S・ウェッブ B・ウェッブ『社会調査の方法』東京大学出版会 1982年 P99
倦怠
苦痛なく苦しみ、意思なく欲し、論理なしに思考すること……それは否定の悪魔にとりつかれ、存在しないものに呪縛されること
フェルナンド・ペソア『不断の書、断章』平凡社(平凡社ライブラリー) 2013年 P237
権力
人類の歴史は、指導力のほんとうのよりどころが魂であることを、いつの時代でも絶えず証明している。人間は魂によって惹きつけられる。権力によって、人は強制される。愛は魂から生まれる。権力によって生み出されるのは不安だけだ
マルコムX『マルコムX自伝』河出書房新社 1993年 P445
行為
行為とは、その目的が明瞭に意識せられている動作の謂である
西田幾多郎『善の研究』講談社(講談社学術文庫) 2006年 P239
幸福
幸福な人間とは、客観的に生きる人である、自由な愛情と広やかな興味をもてる人である、これらの興味や愛情を通して、さらにまた、次にはその代りに彼自身を他の多くの人々にとって愛情と興味の対象にさせるという事実を通して、その幸福を確保するところの人である
バートランド・ラッセル『幸福論』(新版)KADOKAWA(角川ソフィア文庫) 2017年 P329
民衆の幸福とは何か、それは生きる意味、生きる価値への接近と代置することができる
谷川健一『沖縄』講談社(講談社学術文庫) 1996年 P99
人間の幸福は、自由の中に存在するのではなく、義務の甘受の中に存在するのだ
アンドレ・ジッド『サン=テグジュペリ著「人間の土地」序文』新潮社(新潮文庫) 2012年改版 P11
幸福とは幸福を問題にしない時を云ふ
芥川龍之介『「Lies in Scarlet」の言』全集第十二巻 岩波書店 1978年
合理主義
「合理主義」は一つの歴史的概念であり、そのなかに無数の矛盾を包含している
マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店 (岩波文庫) 1989年 P94
国民
滅びゆく国民は、現在に寛大であり、未来を拒否し、過去の偉大さと、半ば記憶にある栄光に満足感を見出す。滅びゆく国民は、変革にたいして防衛的兵器と傭い兵で武装する。偉大さが後退すれば、偉大さにたいする信念も後退する。滅びゆく国民は例外なく、詩は去った、美は枯れたとあきらめる
ジョン・スタインベック『アメリカとアメリカ人』サイマル出版会 1975年(新装版) P208
心
人間の心というものは――とくに感情がからんでくると――期待しているものを発見し、期待していないものに盲目であることに、きわめてたけている
S・ウェッブ B・ウェッブ『社会調査の方法』東京大学出版会 1982年 P59
個性
個性は、自分の選択によるのではなく、達成によって生じる善である
フランカ・オンザロ・バザーリア『現実のユートピア』みすず書房 2019年 P6
国家
国家づくりというのは、「安全で豊かな生活を人々に保障する」ことが目標になります。安全で豊かな社会。それは文明化社会といい換えることができると思います。「国づくり」というのは「文明づくり」と同義語といえるでしょう。(中略)問題を抱えた国には「国家の形」だけはあっても、基本的に欠けた部分がある。その部分が「文明」なのではないだろうか
松本仁一『国家を食べる』新潮社(新潮新書) 2019年 P235
孤独
孤独な人間は、皆一様に〈夜のなかの夜〉に向かって歩き出す散歩者だ
柳美里『窓のある書店から』(新版)角川春樹事務所(ハルキ文庫)2021年 P99
言葉
言葉は わやしの種子 そして
その収穫は いま建築中のもの
アレン・ギンズバーグ『悲しき花粉の輝き』昭森社 1978年 P19
コミュニケーション
コミュニケーションは、文化の創造や維持の源であり、かつ担い手であるような行為課程なのである
タルコット・パーソンズ『文化システム論』ミネルヴァ書房 1991年 P60
作家
社会が政治の腐敗によって危機に瀕しているとき、文学は介入しなければならない。作家はただ社会を楽しませるために書くだけではいけないし、一人引きこもって冷ややかな目で社会をみるだけでもいけない。作家は介入しなければならない
ケン・サロ・ウィワ『ナイジェリアの獄中から』スリーエーネットワーク 1996年 P121
作家というものはある意味で第三の性であるといえる。女性だから男性は書けない、女性しか書けないというのは、真の作家ではない
ナディン・ゴーディマ『アフリカは誰のものか』岩波書店(岩波ブックレット) 1993年
悟り
生きて求めることが悟りだ。生きていたる果てに悟りがあろうはずはない。あるのは死のみ。そうだ。生きていることが求法。死ぬまで、求めて生きるのだ
水上勉『一休を歩く』日本放送出版協会 1988年
サブカルチャー
文化というものは基本的には一群の人びとが共通の問題に照応して生ずるものである。(中略)逸脱とみなされる行動の当事者たちが抱える主要問題は、その行動に関する自分たちの見解が社会の他の成員に共有されないという問題である。(中略)このため、逸脱行動にはしる人びとがたがいに相互作用の機会をもった場合には、彼らは一つの文化を形成するのである。(中略)これらの文化は全体社会の文化の内部で、しかもそれとは独自に機能するため、しばしばサブカルチャーと呼ばれている
ハワード S ベッカー『アウトサイダーズ』現代人分社 2019年POD版 P78-79
差別
人種差別は、生命への侮辱に基礎を置いた一種の哲学である。ある人種が価値の中心、献身の対象であり、その前に他の人種は服従してひざまずかなければならないというのは、傲慢な主張である。ある人種が歴史のすべての進歩に責任を負い、それだけが未来の進歩を保証できるという教義は、まったくばかげている。人種差別というのは、すべての仲違いである。それは身体ばかりではなく、心や精神をも分離させてしまう。必然的にそれは、他のグループに精神的あるいは肉体的な殺人をおかすまでに身を落としてしまうのである
マーティン・ルーサー・キング『黒人の進む道』サイマル出版会 1981年(新装版) P75
すでに客体となり、属性となり、所有の一部となり、名辞となって拡散しつつ固定してゆく意識過程に自分を限定することが差別のはじまりである
谷川雁『無の造形』潮出版 1984年
私は自分にいう。人のことより、お前自身の差別心を刈りとれ。蛇にもきれいな縞柄があるというくせして、蛇をみたら石を投げるお前の根性を刈れ。大衆小説を書く以上、先ずお前がなくしたあとで、この国の大衆がいたって好む差別心と、貧困者に投げるあのあくことを知らぬ侮蔑の眼にむかって挑戦せよ
水上勉『金閣と水俣』筑摩書房 1974年 P222
詩
小説は人と人の織りなす業の世界を描き、人の性と性が衝突すれば詩が生まれる
水上勉『わが文学 わが作法』中央公論社 1982年
一ばん大切なことは詩という概念など存在せず、詩とは在るものではなく、成るものだということである
寺山修司『黄金時代』河出書房新社(河出文庫) 1993年 P89
人に真に共感を誘う詩は実は生きている人間であれば誰しも持ち合わせている天性が発揮されなければ出現しない
今泉準一『元禄俳人宝井其角』桜楓社 1969年 P350
詩は、あらゆる人間的成分の結晶、あらゆる社会的要素の凝結――もっとも、それは単純なものであるが――を創りだす坩堝の底に生きるものである。詩は方法論をもたないひとつの力、本原的で論理をこえた摂理の底知れない深みからあふれでて、事物に意味を与える力である
トリスタン・ツァラ『トリスタン・ツァラの仕事Ⅰ 批評』思潮社 1988年 P154
詩とは何よりも誠実であるべきで、誠実さを犠牲にして「客観的」であったり明瞭であったりすることを私は拒否する
ルイ・マクニース『秋の日記』思潮社 2013年 P9
詩は生命と新鮮さ、活力のある新しい経験を意味している。詩は公式用語と使い古された退屈な表現を敵とするものである
ジェイムズ・リーヴス『詩がわかる本』思潮社 1993年 P224
僕らが漠然と現代詩と呼んでいるものはすべて本来の意味での抒情詩ではないのか。それというのも抒情が胚胎するのは詩人の主体においてのみだからである。社会詩といい、形而上詩といい、シュールレアリスム詩といっても、それが詩人の主体の表現であるかぎり抒情詩のさまざまなヴァリエーションにほかなるまい
渋沢孝輔『渋沢孝輔詩集』思潮社 1971年 P105
多くの人たちは、詩についてきわめて漠然たる考えを持っている。その結果、彼らにとっては、その考えの漠然たること、それ自身が詩の定義なのだ
ポール・ヴァレリー『文学論』角川書店(角川文庫) 1969年改版 P9
死
生の完全な燃焼が死だ/生の躍動と充実の究極が死だ
高見順『敗戦日記』中央公論新社 2005年
国民全体・社会全体が死を恐れ、死を認めないならば、破壊的な自衛手段に訴えざるをえない。戦争、暴動、増加するいっぽうの殺人、その他の犯罪は、私たちが受容と尊厳をもって死を直視することができなくなった証拠かもしれない
E・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間 死とその過程について』読売新聞社 1998年
時間
時間は神の創造した宇宙の性質にすぎない
スティーブン・W・ホーキング『ホーキング、宇宙を語る』早川書房 1994年
音楽は時間芸術だと言われます。時間という直線の上に作品の始点があり、終点に向かって進んでいく。だから時間はぼくにとって長年のテーマでした。(中略)時間は言ってみれば脳がつくり出すイリュージョンだというのが、ぼくの今のところの結論です
坂本龍一『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』新潮社 2023年 P20
Time is an ocean but it ends at the shore
Bob Dylan『Oh,Sister』
時間とは変化の富である、しかし、時計はそれを下手に真似して、富ではない単なる変化にしてしまう
ラビンドラナート・タゴール『迷い鳥』風媒社 2015年 P63
思考
思考とはまず、全体のうちに自己を定位して全体の部分となること、他の諸部分との関係をつうじて自己を定義し、位置づけることでなければならない。思考とは、個人と彼が係わる他の諸部分との差異をつうじて、個人がその自同性を保持することなのだ
エマニュエル・レヴィナス『レヴィナス・コレクション』筑摩書房(ちくま学芸文庫) 1999年 P392
事実
単なる事実は、さまざまな状況や出来事で編まれた網です
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『詩という仕事について』岩波書店 (岩波文庫)2011年 P162
詩人
詩人とは、詩の自由と、それを自由の仮象と視る意識の矛盾する構造を呪われたように自己の内に抱き、現実の政治・社会革命が被支配者の自己権力獲得から権力の消滅までの永久的な革命とならざるを得ないように、その矛盾の構造を限りなく〈人間〉〈全体〉へ止揚しようとする内なる永久革命をつづける者であり、われわれの現存在の二重性、分裂の証人、それとの根源的な闘争者である
黒田喜夫『負性と奪回』三一書房 1972年
詩人は世界の非公認の立法者である
パーシー・ビッシュ・シェリー『詩の擁護』(シェリー詩集)新潮社(新潮文庫)2007年改版 P303
詩人とは文化の分野において他の人間たちにおのれを付け加える人間なのだ
サルヴァトーレ・クァジーモド『クァジーモド全詩集』岩波書店(岩波文庫)2017年 P334
自然
われわれがそこから立ちあらわれてきた対象であり、われわれの諸前提がそこに少しずつ敷設され、ついにそれらが結び合って一つの存在となるにいたった場であり、この存在を支えつづけ、それにその素材を提供しつづけている対象
メルロ=ポンティ『言語と自然』みすず書房 1979年
自然はつねに平らかな落ち着きをもって、人の不幸を目の当たりにし、人の卑しさを寛恕し、人からの責め苦を受けいれるだけだ
ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』新潮社 2024年 P244
思想
思想とは人間の生き方であり、生きる態度である
高島善哉『時代に挑む社会科学』岩波書店 1986年 P121
思想の根底は石畳の十字路である
ポール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』岩波書店(岩波文庫) 2004年 P143
思想は、われわれの感覚の影である。――それはいつでも感覚より、暗く空しく単純である
フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』河出書房新社(河出文庫)2012年 P250
あらゆる思想とは、結局はドラマツルギーのことだ
寺山修司『暴力としての言語』思潮社 1983年 P124
実在
実在はただ直感によってのみ知られることができる。直感は知的同感であり、これによって我々は物の独特で概念的に表現し能わぬものと直接に合一せんがために、その物の内部に身を運び込み、かくて内からそれを捉え得る
三木清『現代の浪漫主義について』(中央公論 1935年6月号)
支配
支配には二種類がある。一つは、支配欲につき動かされた支配だ。もう一つは、誰からも支配されたくないために行う支配だ
フリードリヒ・ニーチェ『ニーチェ全集7 曙光』筑摩書房 1993年
自発性
自発性とは、人間のよき性向もあしき性向も、すべて自由に満足させることを許すような無政府状態のうちにあるのではない。それぞれの社会的価値が、これとは無縁なものによって過大に評価されることも過少に評価されることもなく、まさに正当に評価されるような、そういう精妙な組織のうちにこそある
エミール・デュルケム『社会分業論』筑摩書房 2017年 P608
資本
資本は死せる労働である。それは吸血鬼のごとく生きた労働を搾取することによってのみ生きる。そして資本が生きれば生きるほど資本はそれだけ労働を搾取する
カール・マルクス『資本論』
市民
市民的というのはとくに都市の住民に限らない。農村であろうと漁村であろうと、日本社会を構成する一人の人間として日本国民の一人として、独立の責任をもった人間のことをさすのであって、めいめいがそのような社会なり国民なりの一員であるということを自覚するのが、とりも直さず市民的になるということである
高島善哉『アダム・スミス』岩波書店(岩波新書) 1968年 P58
自由
自由とは自分自身の制約を認識していること
フランカ・オンザロ・バザーリア『現実のユートピア』みすず書房 2019年 P121
自由とは、自分が「自由である」と信ずるところの、一つの幻覚にすぎない
萩原朔太郎『虚妄の正義』講談社 1994年
人間の自由は周知のごとく「……からの自由」ではなくて、「……への自由」であること、すなわち責任を引き受けることへの自由である
ヴィクトール・E・フランクル『死と愛』(新版)みすず書房 2019年 P58
宗教
宗教とは、あらゆるものを創造したとされる最高存在あるいは力とむすびつこうとする、人間の企てである
スティーブ・ビコ『俺は書きたいことを書く』現代企画室 1988年 P107
宗教とは、神聖すなわち分離され禁止された事物と関連する信念と行事との連帯的な体系、教会と呼ばれる同じ道徳的共同社会に、これに帰依するすべてのものを結合させる信念と行事である
エミール・デュルケム『宗教生活の原初形態(上)』岩波書店 1975年 P86
趣味
趣味(すなわち顕在化した選好)とは、避けることのできないひとつの差異の実際上の肯定である。趣味が自分を正当化しなければならないときに、まったくネガティヴなしかたで、つまり他のさまざまな趣味にたいして拒否をつきつけるというかたちで自らを肯定するのは、偶然ではない。趣味に関しては、他のいかなる場合にもまして、あらゆる規定はすなわち否定である。そして趣味とはおそらく、何よりもまず嫌悪なのだ
ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオンⅠ』藤原書店 2020年(普及版) P101
趣味とは感覚の洗練である。だが感覚はなにもしない。受けいれるだけである
ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン『反哲学的断章』青土社 1999年 P168
常識
常識は伝統的な部族の知恵であり、子どもが成長するにつれて学習する「だれでも知っている」雑多な寄せ集めであり、日常生活の決まり文句である
ハワード S ベッカー『アウトサイダーズ』現代人分社 2019年POD版 P184
ショービニズム(盲目的愛国心)
それは、うぬぼれ高き、野蛮な、集団の自己主張にたいする呼び名である。それは個人の判断力や品性を威圧し、その時世を支配している徒党のなすがままに全集団をもってゆく。それは合いことばや空言の支配を生み、そしてそれが行為の決定にさいして、理性や良心にとって代わる。愛国的なゆがみは、思考や判断力のひとつの認められる悪用、曲解であり、それにたいしては教育によって守られるべきである
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P26
勝利
敗北は受容的なものである。しかし勝利は理念であり統一的法則でなければならぬ。日本の文化はこのような勝利の理念的責務に耐え得たかどうか疑わしい
三島由紀夫『小説家の休暇』新潮社 1982年
人格
人格が才能の主人で、才能は人格の召使である
洪自誠『菜根譚』 岩波書店(岩波文庫) 1975年 P156
人権
人権の概念は、それを侵害された人の市民権がある国の法律を超越していますから、救いの手は誰からでも差しのべることができます。権利が脅かされている人と同じ国の市民権が、救い手にあろうとなかろうとかまわないのです
アマルティア・セン『貧困の克服』集英社(集英社新書) 2002年 P97
信仰
信仰は心の無意識の作用であり、その強さは、他の感情と同じように、ただ心の高まりの度合いに比例する
パーシー・ビッシュ・シェリー『飛び立つ鷲』南雲堂 1994年 P133
人種
人種――あるいは一般に理解されている意味の人種――は文化の作用にすぎない
クロード・レヴィ=ストロース『人種と歴史 人種と文化』みすず書房 2019年 P123
人生
人生は幻化に似たり、終に当に空無に帰すべし
陶淵明『全詩文集』筑摩書房(ちくま学芸文庫) 2022年 P106
人生はおしなべて自分が自分の舞を踊って終る。つまり、何処にいてもこの世は幻夢である
水上勉『心筋梗塞の前後』文藝春秋(文春文庫) 1997年 P207
人生の意味は単に問われるべきものではなくて、われわれが人生に責任をもって答えるという意味で、答えられるべきものである。そしてこの答えは常に言葉ではなく行為によって与えられるべきであるのはいうまでもない(中略)したがって、真の答えは行動的な答えであり、日常の具体性における答えであり、人間の責任性の具体的な空間からの答えなのである
ヴィクトール・E・フランクル『死と愛』(新版)みすず書房 2019年 P125
進歩
「進歩」はイデオロギー以上のものである。つまり、進歩とは「正常」なものとして制度化された議会外の行動構造であり、社会を決定的に変えようとするものである
ウルリッヒ・ベック『危険社会』法政大学出版局 1998年 P404
信頼
信頼とは、自己にゆだねられたものに、自己をゆだねることだ
フレデリック・グロ『歩くという哲学』山と渓谷社 2025年 P74
真理
真理とはもっとも根源的な意味で解されるなら、現存在の根本体制にぞくするものである。真理という名称は一箇の実存カテゴリーを意味している
マルティン・ハイデッガー『存在と時間(二)』岩波書店 2013年 P522
真理は考えられた判断であって、単に考えられたに過ぎない判断と真理との識別の根拠は現実感覚による以外になく、この点で現実と交錯するが、考えられた判断という点で現実と異なる
今泉準一『元禄俳人宝井其角』桜楓社 1969年 P250
心理学
心理学は行為である――自己を対象とする省察ではない
アルベール・カミュ『カミュの手帳[全]』新潮社 1992年 P35
神話
神話とは、正しいと証明されたからではなく、それを認めると便利だからということで認められる説明である
デヴィッド・リンドリー『物理学の果て』青土社 1994年
人間には、生まれつき神話を生みだす力がある。数奇な運命をたどった者の人生に驚くべき不思議な出来事を探し出して神話を作り、それを頭から信じこむ。神話は、平凡な人生に対するロマンチックな抵抗なのだ
サマセット・モーム『月と六ペンス』新潮社(新潮文庫) 2014年 P8
睡眠
睡眠は死から借りた行為である。睡眠は生命を維持するために、死から借りるものである
アルトゥール・ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』中央公論新社 2004年
スティグマ
スティグマという言葉は、人の信頼をひどく失わせるような属性をいい表わすために用いられるが、本当に必要なのは明らかに、属性ではなくて関係を表現する言葉なのだ、ということである
アーヴィング・ゴッフマン『スティグマの社会学』せりか書房 2001年改訂版 P16
スティグマとは、スティグマのある者と常人の二つの集合に区別することができるような具体的な一組の人間を意味するものではなく、広く行われている二つの役割による社会過程を意味しているということ、あらゆる人が双方の役割をとって、少なくとも人生のいずれかの出会いにおいて、いずれかの局面において、この過程に参加しているということ、である
アーヴィング・ゴッフマン『スティグマの社会学』せりか書房 2001年改訂版 P231
最もスティグマの減少に有効な方法は、社会への統合である。宗教や人種、経済などの障壁は、異なる人々がともに働き、ともに遊び、ともに学び、ともに生活することを求められたとき、最も効果的に取り除くことができる
チャールズ・A・ラップ/リチャード・J・ゴスチャ『ストレングスモデル』金剛出版 2014年 P358
スピリチュアリティ
スピリチュアリティは、その人に希望、心の慰労、人生の意義や目的を与える信念あるいは実践、またはより大きな世界につながりをもつことを言う
チャールズ・A・ラップ/リチャード・J・ゴスチャ『ストレングスモデル』金剛出版 2014年 P384
生活
生活は利害関心を満たすうちにある。というのは、社会における「生活」というのは、物質と社会的環境に費やされる行為と努力の履歴であるからだ
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P29
生産
生産とは、まず人間の生産であり、衣食住のための物的生産であり、つぎに社会的生産であり、最後に文化的生産である。これをひっくるめて言えば、新しい歴史の生産である
高島善哉『社会科学の再建』新評論 1981年 P209
政治
われわれにとって政治とは、国家相互の間であれ、あるいは国家の枠の中で、つまり国家に含まれた人間集団相互の間の場合であれ、ようするに権力の分け前にあずかり、権力の配分関係に影響を及ぼそうとする努力である
マックス・ヴェーバー『職業としての政治』岩波書店(岩波文庫) 2020年 P10
政治家
西海岸に着いたときは一文無しで
親父は腹をすかし、物乞いするより他なくて
じゃがいも1,2個乞食した
女房がそれでシチューを作り
子供らに少しばかりついでやった
だけど水っぽいシチューでね
それをすかして雑誌が読めるほどだった
そのとき思ったものだった
それがもっとうすければ
少しはましな政治家どもには
ちゃんとものごとを見通せるはずだと
ウディ・ガスリー『Talking Dust Bowl Blues』
誠実
誠実は美徳ではなく、情熱である。それゆえそれは決して寛大ではない
アルベール・カミュ『カミュの手帳[全]』新潮社 1992年 P423
正常
正常な状態とは、現実を尊重する態度を維持することである
ジークムント・フロイト『人はなぜ戦争をするのか』光文社(光文社古典新訳文庫) 2008年 P104
精神病
精神病とは、この病が発症している様々な社会的背景に根ざした狂気の表現方法である
フランコ・バザーリア『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』岩波書店 2017年 P213
世界
世界は数え切れない精神から発生する想像力の流れのダイナミックな交差点である
フランコ・ベラルディ『脱走論』青土社 2025年 P50
病人が居て健康な人が居て
悪人が居て善人が居て
揺れ動く者が居て微動だにしない者が居て
そんな二元論では
世界はつくられない
三角みづ紀『錯覚しなければ』思潮社 2008年 P11
禅
禅とは、現生から出発して、諸法の実相たることを確信するにある。それによって迷いを去り、仏を見、自己をその仏にしようとする一派である
水上勉『水上勉仏教文集 第一巻「白隠」』筑摩書房 1982年
善
人格の実現というのが我々にとりて絶対的善である
西田幾多郎『善の研究』 講談社(講談社学術文庫) 2006年 P346
善悪
善悪は人に生まれついた天性
苦楽は各自に与えられた天命
オマル・ハイヤーム『ルバイヤート』岩波書店(岩波文庫) 1979年改版 P35
人の心、元より善悪なし
善悪、縁によっておこる
道元『正法眼蔵随聞記』
どんな人間の性格にも善と悪がある しかし 悪は抜きがたく 善は子どものころにすでに息絶える
エーリッヒ・ケストナー『人生処方箋・続』思潮社 2013 P61
善と悪とは、わたしたちの欲求と嫌悪を表す名称である。それは気質・習慣・主義が異なればおのずと異なったものとなる
トマス・ホッブス『リヴァイアサン1』光文社 2014 P275
潜在能力
潜在能力は実質的な自由を反映したものであると言える。機能が個人の構成要素である限り、潜在能力は個人の福祉を達成しようとする自由を表している
アマルティア・セン『不平等の再検討』岩波書店(岩波現代文庫) 2018年 P80
戦争
文化は没落しかかっています。戦争がこのような事態を生み出したのではありません。戦争それ自体は、ただ、その一つの現れにしかすぎません
アルベルト・シュヴァイツァー『文化の没落と再建』世界思想教養全集21 河出書房新社 1963年 P27
戦争を学ぶこと。それは単なる悲劇に涙することでも、「今の日本は平和でいい」と安易に結論づけることでもない。その犠牲を生んだシステム、それを生みだした国家や軍隊の本質を見抜くこと
大矢英代『沖縄「戦争マラリア」』あけび書房 2020年 P207
戦争はすべてを失うことを、本来の自分とは違った人間になることを教える。すべては好みの問題となってしまう
アルベール・カミュ『カミュの手帳[全]』新潮社 1992年 P113
戦争とは一種の暴力であり、それが目指すのは相手に自分の意志を強要することにある
カール・フォン・クラウゼヴィッツ『戦争論(上)』岩波書店(岩波文庫)1968年 P29
戦争は人間の殺し合いであり、生存を否定しあうことなのだから、民主主義に反するものである。また戦争は、一部の「死の商人」(戦争を利用して的にも味方にも兵器や物資を売って儲けるもの)を除いては、国民の暮らしや健康を損なうものである。したがって社会保障に反する状況をつくり出すものである
真田是『社会保障と社会改革』かもがわ出版 2005年 P41
人間の集団というものは、暴力団から国民全体にいたるまで、それぞれの集団のアイデンティティを利用して他の集団を攻撃・破壊するが、これは破壊される恐怖の裏返しの表現である。戦争は、死を直視し、それを克服し、死なずに生き残りたいという欲求、すなわち、特異な形での死の否認に他ならない。〈中略〉だとすると、国の指導者、つまり国家間の戦争と平和を最終的に決定する人びとが死をどのように見ているかを研究すれば、平和への手がかりがつかめるかもしれない。私たちのだれもが死について考え、死に対する不安にうまく対処し、他の人にもその考えに慣れるよう手助けをすれば、私たちの周囲の破壊行動も減るのではないだろうか
E・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間 死とその過程について』読売新聞社 1998年
創造
創造とは平和としあわせの堆肥となること
谷川雁『原点が存在する』 弘文堂 1958年
創造はすべて幻想である
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P259
ソーシャル・ケースワーク
ソーシヤル・ケースワークは、さまざまな心理・社会的問題をもつ人びとを援助する一つの技法である。その援助技法には調査、診断、また治療の諸課程が含まれる
F・P・バイステック『ケースワークの原則』誠信書房 2006年 P211
速度
速くなければならぬ、と私は思っていた。
あらゆる文明の権力から、自らを守るためには速度が必要なのだ
寺山修司『書を捨てよ、町へ出よう』芳賀書店 1967年
尊敬
あなたを尊敬するかぎり、世界は貧しくならない
ラビンドラナート・タゴール『ギタンジャリ』風媒社 2017年 P111
退屈
退屈は絶えざる一つの警告なのである。何が退屈を生み出すのであろうか。それは活動しないということである。しかし、行動はわれわれが退屈から逃れるためにそこにあるのではなくて、われわれが活動しないことから逃れ人生の意味を正しく認めるように、退屈がそこにある
ヴィクトール・E・フランクル『死と愛』みすず書房 2019年 P118
退行
退行とは、圧力をうけたシステムが、以前の発展段階において支配的かつ適切だったパターンに戻るという意味である
タルコット・パーソンズ『宗教の社会学』勁草書房 2002年 P157
第三者
もともと、社会には「第三者」などというものは存在しないのだ。それにもかかわらず、自分の顔見知りでない人間を「第三者」だと思いこむことは想像力の欠如である。そして、「第三者」を生みだす負の想像力こそ、現代の政治と犯罪の残忍さの母胎となるものだ
寺山修司『時代のキーワード』思潮社 1993年新装版 P156
祟り
祝福やたたりについての観念は、人間が知りえた繁栄や災難の大きな実例についての事後からの説明である
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P17
旅
旅っていうのは別にかっこよく旅するんじゃない。人の力を認識するのが旅なんです
田村隆一『詩人の旅』中央公論新社 2019年 P252
旅には性格があり、気性があり、個性があり、独自性がある。旅は、それ自体が人間であり、おなじものは二つとない。どんなにプランをたてても、どんなに安全に気を配っても、どんなに警戒しても、どんなに抑えこんでも、意味がない。何年も奮闘するとだれもが知るようになることだが、われわれが旅をするのではなく、旅がわれわれを引っぱっていく
ジョン・スタインベック『チャーリーとの旅』岩波書店 (岩波文庫)2024年 P14
探究
われわれは探究をやめない
そしてあらゆる探究の終りは
われわれの発足の地に達し
その地を初めて見ることなのだ
T・S・エリオット「四つの四重奏」『エリオット全集1』中央公論社 1971年
知覚
知るとは、接(まじわ)るなり
知覚するとは、(五感が対象を認識しようとして)外界の事物に交接する行為である
墨子『墨子』講談社(講談社学術文庫) 1998年 P210
中立
二人の人間が争っていて、一方が他方よりもはるかに強いとき、中立でいることは決して公正でも、公平でも、不偏不党でもない。なぜならこの場合、中立でいることは、実際は力のあるほうに味方するのと同じだからである
デズモンド・ツツ『南アフリカに自由を』サイマル出版会 1983年 P58
沈黙
沈黙は行動である。行動に対する批判として、それ自体が行動である
竹内好『魯迅』 日本評論社 1944年
沈黙とは、あらゆる思想のぎりぎりの表現、あらゆる努力のもっとも単純な形態である
イヴォ・アンドリッチ『サラエボの鐘(旧ユーゴ短編集)』恒文社 1997年
罪
罪とは絶望である。その度の強まったものが、自己の罪について絶望する、という新しい罪である
セーレン・キルケゴール『死にいたる病』筑摩書房 (ちくま学芸文庫)1996年 P201
哲学
哲学は、最も強く抱かれている本能的信念から始め、ひとつひとつ取り出してはそこから余計な混ざりものをそぎ落としながら、本能的信念の階層構造を示さなければならない。そして最終的に提示される形式では、本能的信念は衝突しあわず、調和した体系をなすことを示さなければならない
バートランド・ラッセル『哲学入門』筑摩書房(ちくま学芸文庫)2005年 P32
天才
天才とは、揺るぎのない自分の世界を現実と対峙させることが可能なひとを指す
柳美里『窓のある書店から』(新版)角川春樹事務所(ハルキ文庫) 2021年 P122
同感
同感はその情念を考慮してよりも、その情念をかきたてる境遇を考慮して起こる
アダム・スミス『道徳感情論(上)』岩波書店(岩波文庫) 2003年 P31
統合
解放と統合の間には、理論的あるいは社会的な分離は存在しない。われわれのような社会では、解放は統合なしでおきることはできず、統合もまた解放なしで実現することはないのだ。ここでいう統合とは、倫理的と政治的の両方の意味のものである。一方では、統合とは真の意味でのグループ相互間の、個人相互間の生活である。他方では、それは力をおたがいに分けあうことでもある
マーティン・ルーサー・キング『黒人の進む道』サイマル出版会 1981年(新装版) P65
統合とは、お互いの尊厳を認め合い、共通の基本的な価値と権利を認め合うという人と人との関係がベースになっている。もしそのような認識がなければ、疎外、隔離、排斥がおこるだろう
ベンクト・ニィリエ『ノーマライゼーションの原理[増補改訂版]』現代書館 2000年 P102
道徳
道徳律というものは人間の最大発見である。他者の中に自己を実現することが多ければ多いほどますます人は真実になる、というこの大変な真実に関する発見である。この真実は主観的な価値づけであるばかりでなく、なおまたわれわれの生活のあらゆる場面にも明示されている。そして愛国主義的信条だとして、道徳的盲目を懸命になって培っている諸国民は、突然の不自然な死に方で彼らの存在を終わるであろう
ラビンドラナート・タゴール『タゴール著作集 第八巻
人生論・社会論集』第三文明者 1981年
道徳論は、我々はどうすれば自分を幸福にするかということについての教えではなくて、どうすれば幸福を受けるに値するようになるべきであるかということについての教えである
イマヌエル・カント『実践理性批判』岩波書店(岩波文庫) 1979年
道徳の与へたる恩恵は時間と労力との節約である。道徳の与へたる損害は完全なる良心の麻痺である
芥川龍之介『侏儒の言葉』岩波書店(岩波文庫) 1959年
徳
万物を生みだし、養い、生育しても所有はせず、恩沢を施しても見返りは求めず、成長させても支配はしない。これを奥深い徳という
老子『老子』岩波書店(岩波文庫) 2008年 P45
富
「富」は人間の心を変え、「貧」もやはり人間の心を変える。けれど、「貧」時の肌をなでる清風は、人間の自然に近い「富」だ
水上勉『金閣と水俣』筑摩書房 1974年 P64
ナショナリズム
政治的な単位と民族的な単位とが一致しなければならないと主張する一つの政治的な原理である
アーネスト・ゲルナー『民族とナショナリズム』岩波書店 2000年 P1
難儀
どんな種類の難儀でも、解決に必要なのは、情緒的快活さではなく、建設的な思考である
バートランド・ラッセル『人生についての断章』みすず書房 1979年 P92
日常性
「日常性」は生活の全体性・現実性の基盤としての一つの思想といえる
右田紀久恵『地域福祉総合化への道』ミネルヴァ書房 1995年 P27
人間
人間は最近の発明にかかわるものであり、二世紀とたっていない一形象、われわれの知のたんなる折り目にすぎず、知がさらに新しい形態を見いだしさえすれば、早晩消えさるものだ
ミシェル・フーコー『言葉と物』新潮社 1974年 P22
人間とは、世界へ、同類へ向かう運動そのものである。奴隷化あるいは制服を産み出す、攻撃性の運動である。また愛の運動、自己の贈与であり、論理的方向づけと呼ぶにふさわしいものの最終項でもある
フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』みすず書房 1998年 P64
忍耐
忍耐とは、何かが起きるのを座視することではなく、私たちが全面的に身をゆだねる相手への関与の一つのあり方なのである
ミルトン・メイヤノフ『ケアの本質』ゆみる出版 2001年 P44
ノーマライゼーション
ノーマライゼーションの原理は、知的障害やその他の障害をもつ全ての人が、彼らがいる地域社会や文化の中でごく普通の生活環境や生活方法にできる限り近い、もしくは全く同じ生活形態や毎日の生活状況を得られるように、権利を行使するということを意味している
ベンクト・ニィリエ『ノーマライゼーションの原理[増補改訂版]』現代書館 2000年 P130
能動
能動とはたんに「何かをする」ことではなく、内的能動、つまり自分の力を生産的に用いることである
エーリッヒ・フロム『愛するということ』紀伊國屋書店 2020年 P190
走る
走ることは思想なのだ
ロンジュモーの駅馬車からマラソンのランナーまであらゆる者は走りながら生まれ、走りながら死んだ
寺山修司(ロング・グッドバイ)『寺山修司全詩歌句』思潮社 1986年 P173
犯罪者
犯罪者は国家の競争相手であり、国家の暴力独占権をおびやかす存在である
ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー『政治と犯罪』晶文社 1983年
万物
万物は間断なく盛大である
老子『老子の思想』張鐘元著 講談社 1987年 P54
万物は流転する、たちどまらない、ふりかえらない。どんなちからでも制止できない。万物は流転する
ラビンドラナート・タゴール『ギタンジャリ』風媒社 2017年 P105
美
美しいものは どんなものであれその奥に何らかの痛みを宿している
ボブ・ディラン『NOT DARK YET』
「美は真理の本質の運命的な贈り物である」(1)とハイデッガーは書いているが、私は逆だと思う。すなわち、美は真理の不在の(ひとつとはかぎらない)運命である
(1)『ハイデッガー全集8 思惟とは何の謂いか』東京大学出版会 2021年
フランコ・ベラルディ『脱走論』青土社 2025年 P209
必要
必要は、物事が成立する理由とみなされる。実のところ、必要は、成立したものの結果にすぎないことがよくある
フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』河出書房新社(河出文庫) 2012年 P258
必要はもっとも確実たる理想である
石川啄木『時代閉塞の現状・食うべき詩』岩波書店 (岩波文庫)1978年
批判
批判というのは直下ではなくて、対立的に物事を考えることだ(中略)その対立をまとめなければ納得できないだろう
水上勉『泥の花』河出書房新社 1999年
批判というものは否定ではなくして識別であり、追放ではなくして摂取であり、懲罰ではなくして活用である
高島善哉『民族と階級 現代ナショナリズム批判の展開』現代評論社 1970年
批判は、暗示が制限され、正される作用である。人が軽信や感情や誤った考えより防衛されるのは、批判によってである。批判の力は、教育がおもに訓練すべきことであある(中略)高度に訓練された判断には、自分自身の考えを正し、選択すること、そして固定観念を避けることが要求される。最高の批判とは、自分自身を批判することなのである
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P35,36
己が境界にあらざるものをば、争ふべからず、是非すべからず
吉田兼好『徒然草 第百九十三段』
比喩
比喩は抽象的な概念を理解する基礎であるばかりか、「心の理論」に並行する形で、人間の知性の進化に不可欠なもの
フランク・ファランダ『恐怖と不安の心理学』ニュートンプレス(ニュートン新書) 2022年 P82
病的
病という言葉は、ただの空語であるか、あるいはなにか避けることのできるものをさししめす言葉である。もちろん、避けることのできるものがことごとく病的なわけではないが、病的なものは、少なくともたいていの者にとって避けることのできるものである。
エミール・デュルケム『自殺論』中央公論新社(中公文庫) 2020年(改版) P622
平等
真の平等に到達することを願うなら、実際問題として地球の北側でも南側でも、いたるところで蔓延している性差別や社会的差別、民族、人種に対する差別と闘うことができる指標や手続きを発展させることが急務である。しかし実際には、アイデンティティを硬直化させることなく、根強い偏見と闘うことそのものが、大きな困難のひとつなのだ
トマ・ピケティ『平等についての小さな歴史』みすず書房 2024年 P151
異なる領域において平等が要求するものは互いに整合的であるとは限らない。というのは、人間はあまりに多様な存在だからである。一つの領域における平等は、他の領域における重大な不平等を伴うものである
アマルティア・セン『不平等の再検討』岩波書店(岩波現代文庫) 2018年 P233
貧困
貧困とは、(中略)絶対的窮乏と対照的な相対的剥奪を反映し得る概念である。したがって、深刻な飢餓が生じていない時ですら貧困は存在し得るし、極貧とみなせることもあり得る。一方、飢餓は貧困を意味する。なぜなら飢餓の特徴である絶対的剥奪は、相対的剥奪という観点から何が言えるかに関わりなく、貧困と診断されるのに十二分だからである
アマルティア・セン『貧困と飢餓』岩波書店 2000年 P61
貧困の意味するところは、不十分な住居、移動の制限、余暇・教育・人間関係・雇用の機会の制限である
チャールズ・A・ラップ/リチャード・J・ゴスチャ『ストレングスモデル』 金剛出版 2014年 P27
貧困とは、福祉水準が低いということではなく、経済的手段が不足しているために福祉を追求する能力がないことである
アマルティア・セン『不平等の再検討』岩波書店 (岩波現代文庫)2018年 P194
貧困が問題なのは、(潜在能力の欠如に陥らないための)経済的手段が不足しているからではあるが、もっと基本的なのは必要最低限の潜在能力が欠如していることである
アマルティア・セン『不平等の再検討』岩波書店(岩波現代文庫)2018年 P195
不安
不安は、自分の幸福に対する何らかの脅威が将来発生する可能性に対する早期警告システム
デビッド・A・クラーク、アーロン・T・ベック『不安・心配と上手につきあうためのワークブック』岩崎学術出版社 2024年 P46
内的異常状態の警報を表していて、身体体験の自発性が欠如する中で自分の体験と自己を受け入れられなくなった状態である。この不安は臨床上、懐疑とためらいによって曖昧で多義的な状態の中で明らかになる
フランカ・オンザロ・バザーリア『現実のユートピア』みすず書房 2019年 P91
不安とは、快と不快の連鎖が特定の形で感受されること、この情動が感受される際に、これと対応して放出性の神経支配が発生すること、そして、これが知覚されること、それらが一体になったもの
ジークムント・フロイト『人はなぜ戦争をするのか』光文社(光文社古典新訳文庫) 2008年 P191
風景
風景とは言いかえれば、人の思い出の歴史のような気もする。風景を眺めているようで、多くの場合、私たちは自分自身をも含めた誰かを思い出しているのではないか
星野道夫『アフリカ旅日記』メディアファクトリー 1999年 P40
フォークウェイズ
フォークウェイズは、欲求を充足しようとする努力から起こってくる個人の習慣であり、社会の慣習である
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P4
武器
日本は自己防衛の近代武器の入手を考えてはならないとわたしは一言たりともいってはいない。しかし自己保存の本能を超えるものであってはなるまい。本物の力は武器を使う人にあること、武器それ自体にはないこと、そして人が力を欲するあまり、己の魂を売って武器を増やすとき、敵以上に大きい危険は己れ自身である、ということを日本は知るべきである
ラビンドラナート・タゴール『タゴール著作集 第八巻
人生論・社会論集』第三文明者 1981年
福祉
福祉は、平和のシンボルである。福祉を充実させることこそ、平和国家への道であると確信をもって主張したい
阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房 2008年 P154
新しい福祉は、福祉ニードに対して、あらゆる資源を動員して対応する理念に立っている。それを地域社会を基盤に実現しようとするところに、地域福祉の意義がある
阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房 2008年 P100
社会保障体系を制度として運用する国とその利用者としての個人および労働者階級の間に、また運用組織・単位としての国と地方自治体、地方自治体と住民の間に、民主主義原理が磁石として存在しなけらばならない。この磁石をはずすとき、個人・労働者階級・地方自治体の自由喪失と、国家管理・国家統制がはじまる。この磁石をはめ込んで、はじめて福祉国家の理想と現実は、国のレベルと地方自治体のレベルにあらわれる
右田紀久恵『社会福祉の歴史〔新版〕』有斐閣 2001年 P80
真の「福祉」であるためには、個人の主体的にしてかつ個別的な要求(needs)が充足されなくてはならない。その意味では、「福祉」は終局的には個別的処遇である
岡村重夫『地域福祉論(新装版)』光生館 2009年 P9
不幸
すべての不幸はなんらかの種類の不統一、あるいは融合統一の欠如にもとづいている。そして、自分自身の内部におけるこのような不統一は意識的精神と無意識的精神との協力の欠如によるものである
バートランド・ラッセル『幸福論』(新版)KADOKAWA(角川ソフィア文庫) 2017年 P335
すべての人の不幸は、皆が常に眺める側に立ち、またその見ているものを自分に従属せしめるというところから来ている
アンドレ・ジッド『地の糧』(新版)新潮社 (新潮文庫)2023年 P45
不条理
不条理の問題のすべては、価値判断と事実判断とに収斂されるものでなくてはならない
アルベール・カミュ『カミュの手帳[全]』新潮社 1992年 P225
不満
不満というものは、悲惨な状態によって自然に生まれてくるわけではないし、不満の強さも生活の悲惨さと正比例するものではない
むしろ悲惨な状態がどうにか耐えられるものであるときに、そして生活状態が改善されて、理想的な生活が手に届くのではないかと思われたときにこそ、不満がもっとも強くなる。苦しみの原因がほとんど取り除かれそうになってきたときにこそ、そうした苦しみはもっとも強く感じられるのである
エリック・ホッファー『大衆運動』紀伊國屋書店 2022年 P52
文化
文化とは本質的に、人生のさまざまな問題に対する、社会の複合的な解答である
スティーブ・ビコ『俺は書きたいことを書く』現代企画室 1988年 P182
文化とは人間の内部にある動物的なものを次第に馴致して行くことである。文化の過程は馴致の過程であり、この過程は、自由を渇望する動物的本性の側かわの憤激を呼ぶことなくしては遂行されない
C・G・ユング『無意識の心理』(新装版)人文書院 2017年 P27
文法
人間言語の生成文法は高度に制限された種類の基底規則の体系と、基底規則に準拠して形成された深層構造を表層構造へ写像する文法変形の集合と、普遍的音声アルファベットで表層構造に音声解釈を付与する音型規則の集合とを含んでいる
ノーム・チョムスキー『言語と精神』河出書房新社 1996年改訂版 P259
文明
文明とは、理智が本能の眞似をする事である
芥川龍之介『「Lies in Scarlet」の言』全集第十二巻 岩波書店 1978年
文明は多かれ少なかれ高度に洗練されたもののなかにあるのではない。そうではなくて、それは一つの民族全体に共通する意識のなかにある。そしてその意識は決して洗練されてはいない。それは単純で真っ直ぐなものでさえある。文明を選良たちが作り上げたものとみなすことは、まったく別のものである文化と文明とを同一視することだ
アルベール・カミュ『カミュの手帳[全]』新潮社 1992年 P33
文明とは、自由なるエネルギーの、合理的な、意志と意図とを以って招き寄せられた「目的に適った」昇華の謂である
C・G・ユング『無意識の心理』(新装版)人文書院 2017年 P81
平和
平和とは一切の敵意が終わること
カント『永遠平和のために』岩波書店(岩波文庫) 1985年 P13
平和とは約束事からなる一つのシステムにすぎないとということであり、それは諸々の象徴の均衡、本質的に信用に基づいた構築物である
ポール・ヴァレリー 「東洋と西洋」『精神の危機』岩波書店(岩波文庫) 2010年 P305
平和な国家は、その独立を守るだけの力を持っていなくてはならないが、その軍備によって国家が軍国主義化されてはならないし、その軍備を十分に規制することができなくてはならない。経済的に言えば、他国に支配されざるをえない国家も、他国を支配しなければならない国家も、ともに平和な国家ではない。そして国家の権力は制約されていなければならず、言論の自由の欠如、多数の専制、ある理念への狂信などは、国家権力の制約をいちじるしく困難にするものとしてしりぞけられなければならない
高坂正堯『国際政治』中央公論新社 (中公新書)2017年改版 P216
偏見
ある集団に所属している人が、たんにその集団に所属しているからとか、それゆえにまた、その集団のもっている嫌な特質をもっていると思われるとかという理由だけで、その人に対して向けられる嫌悪の態度、ないしは敵意ある態度である
ゴードン・W・オルポート『偏見の心理』培風館 1968年 P7
暴力
暴力の本質は、その威力ないしは何らかの手荒な力を行使してしかじかの結果を手にすることにあるのではなくて、所与の法/権利の秩序に脅しをかけたりそれを破壊したりすることにある
ジャック・デリダ『法の力』法政大学出版局 1999年
ボランタリズム
ボランタリズムは、社会福祉の実践を、問題によっては国家や自治体が直接行うより、自由で自主的な意思をもつ民間団体や住民が行うほうがよいと考える思想である。それは、無報酬で時間や労力を提供するボランティアの根源となる思想でもある
阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房 2008年 P97
本
世界はすべて、ひらかれた本である。問題はどのように「読みとる」べきか、だ。すなわち、
本は、あらかじめ在るのではなく、読者の読む行為によって、〈成らしめられる〉無名の形態に他ならない
寺山修司『幻想図書館』河出書房新社(河出文庫) 2006年 P130
学び
学ぶとは、知識や技術を単に増やすことではなく、根本的に新しい経験や考えを全人格的に受けとめていくことをとおして、その人格が再創造されることなのである
ミルトン・メイヤノフ『ケアの本質』ゆみる出版 2001年 P29
名利
名利の路を践むことなかれ
名利 わずかに心に入らば
海みずもまた澍ぎがたし
良寛『僧伽』
民主主義
千差万様に生きる人間にとって、人間はその顔、軀つきがちがうように、精神内容もまたちがう。だから、その存在自体が民主主義なのである
水上勉『金閣と水俣』筑摩書房 1974年 P60
民主主義とは、組織の形態ではなく、毎日の生活習慣である
メアリー・E・リッチモンド『ソーシャル・ケースワークとは何か』中央法規出版 1991年 P155
民族
民族は人間が作るのであって、民族とは信念と忠誠心と連帯感によって作りだされた人工物なのである
アーネスト・ゲルナー『民族とナショナリズム』岩波書店 2000年 P12
民族中心主義(自文化中心主義:ethnocentrism)
民族中心主義というのは人々をして、かれらのフォークウェイズにおけるすべてのことを、それは特有のものであり、それが自らを他と異ならしめているのだ、と誇張し、強調する方向へと導くということである。それゆえ、民族中心主義というのはフォークウェイズを強化することになるのだ
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P22
妄想
妄想とは、固定化された考えのことで、それらは現実と調和せず、文化的規範から逸脱し、理屈にあわない考えです
ジョエル・レビー『心理学の基礎講座』ニュートンプレス(ニュートン新書) 2022年 P215
モーレス
モーレスは、われわれがみんな無意識のうちに参加している社会的な儀礼である。労働時間、食事時間、家族生活、男女の社交、礼儀正しさ、娯楽、旅行、休日、教育、定期刊行物や図書館を利用すること、その他無数にある生活のささいなこと、といった現今の習慣はこの儀礼の下にある
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P80
目標
目標はすべて理想である
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P259
物語
ほんとうの物語は、みんなそれぞれはてしない物語なんだ
ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』岩波書店 1982年 P587
模倣
他人による籠絡であり、自己への他人の侵入であり、それはまた自分がその面前にいる人の身振りや動作、気に入った言葉、行為のしぐさなどを、自分に引き受けようとする態度
モーリス・メルロ=ポンティ『眼と精神』みすず書房 1966年 P176
モラル
モラルといわれる言葉には二つの意味があることを注意したい。一つは人間がその内から発する行為、したがってたんに本能や衝動によって動くのではない人間として責任のとれる行為である。モラルのもう一つの意味は、社会的という意味である。私たちが道徳という言葉をきくと、どうやら前の意味だけをとって後の意味を忘れがちになる。これは日本人の道徳観念に社会性が乏しいことと大きな関係があるといわなければなるまい
高島善哉『アダム・スミス』岩波書店(岩波新書)1968年 P77
闇
光の欠乏した状態が闇だというばかりではなく、闇の欠乏した状態が光だということもできる。そして、闇の中でなければ見ることのできぬ「もう一つの世界」というのもある
寺山修司『地平線のパロール』河出書房新社(河出文庫) 1993年 P182
憂鬱
憂鬱はひとえに褪めた情熱に由来する
アンドレ・ジッド『地の糧』新潮社 2023年(新潮文庫)(新版) P14
勇気
真の勇気というものは、極端な臆病と向こうみずの中間にいる
ミゲル・デ・セルバンテス『ドン・キホーテ』岩波書店 2001年
夢
夢は切断された果実である
左川ちか『左川ちか全集』書肆侃侃房 2022年 P93
夢が死んだら
人生は羽を砕かれた鳥だ
飛ぶことが出来ない
ラングストン・ヒューズ『友愛・自由・夢屑・霊歌』コールサック社 2021年 P72
余暇
余暇は自由時間の享受、充足、および機能的休息などというよりは、むしろ非生産的時間の消費と定義される
ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』紀伊國屋書店 2015年 P272
欲望
欲望は本質的に模倣的である(中略)欲望は手本となる欲望から写し取られ、欲望はその手本と同じ対象を選び取る
ルネ・ジラール『暴力と聖なるもの』法政大学出版局 1982年
ラベリング
ラベリングは単なる命名やカテゴリー化ではなく、社会にとって正規の分類図式から拒否された「剰余」ともいうべき普遍的なカテゴリーに、人類を分類することなのである。これがラベリング過程の認識論的本質である
ハワード S ベッカー『アウトサイダーズ』現代人分社 2019年 P228
リカバリー
リカバリーとは、症状を体験し、スティグマとかトラウマに直面し、そしてその他のつまずきのまっただ中にあって、いかに人生を生きているかということである
チャールズ・A・ラップ/リチャード・J・ゴスチャ『ストレングスモデル』金剛出版 2014年 P19
リスク
リスクは、決定者自身による観察(自己観察)も含めて、決定を観察する際の観点である
二クラス・ルーマン『リスクの社会学』新泉社 2014年 P127
理性
理性とは、ある想念が他の想念にたいしてもつ関係を、それらがどのようにして生まれたかは別として、考察する精神である
パーシー・ビッシュ・シェリー『詩の擁護』(シェリー詩集)新潮社(新潮文庫) 2007年改版 P248
理性とは、人間によって認識され、人間の生命の活動のよりどころとなるべき法則である
レフ・トルストイ『人生論』
理想
理想はまったく非科学的である。それは事実とほとんどつながりのない一つの幻想である。(中略)ある人が自分の努力で理想を実現しようとしているばあいにその理想が想像力を形づくるとき、理想は有用でありうる。というのはそこでは理想と行為のプログラムは同じ意識の上にあり、したがって理想の欠点は軽減され、取り除かれるからである
ウィリアム・グラハム・サムナー『フォークウェイズ』青木書店 1975年 P258
理由
理由というものはたいてい、事実が起きたあとで、説明が必要になったときに、つけられるものである
ジョン・スタインベック『アメリカとアメリカ人』サイマル出版会 1975年 P173
良心
良心とは厳粛なる趣味である
芥川龍之介『侏儒の言葉』岩波書店(岩波文庫)1959年
歴史
歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去の間の尽きることを知らぬ対話である
E・H・カー『歴史とは何か』岩波書店 (岩波新書)1962年
大体において、歴史とは、われわれがかくあれあしと望んだものである
ジョン・スタインベック『アメリカとアメリカ人』サイマル出版会 1975年 P175
歴史とは、それを見るこっちの心だというしかあるまい。これが「事実」だと、一枚の紙をみせられても、瓦をみせられても、ただの紙切れや瓦塊とみる心なら、歴史は向こうで口を閉じる。厄介なことである。
人は忘れることで生きてゆく。忘れないように書きのこそうとしても、手が思うとおりうごかなくて、嘘でしめくくる。われわれの「日記」をみれば、いい例証だ。嘘も真も歴史の顔のように思う
水上勉『わが文学 わが作法』中央公論社(中公文庫) 1982年
レジリエンス(リジリエンス)
愛する人の死に対処する場合や、戦争、災害、疫病、テロなどといった惨事に遭遇した場合に、リジリエンスが認められる。こういった出来事を恐れるが、しかしこのような出来事が生じてしまったら、可能な限りそれに対処するしか術はない。幸いなことに、ほとんどの人がこういった出来事に巧みに立ち向かう。この意味で、喪失の苦痛を耐え忍ぶ能力は特別なものではない。むしろ逆境の中で強く生きる人間の一般的な能力を示す一例である
ジョージ・A・ボナーノ『リジリエンス』金剛出版 2013年 P251
労働
労働は欲求の抑制であり、消失の延期である
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル『精神の現象学 上巻』岩波書店 (岩波文庫) 1973年
労働の観念は自然法哲学を経済学に媒介する役目を持っている。労働は自然に対する人間の働きかけであり従って財産の基礎である。自然法哲学においてはすべての人間が平等自由と考えられているから、労働は自由平等なる人間の力の発動であり、そこからして財産の絶対不可侵とそれに基づいて、等価交換の原則すなわち流通の正義並びにこれを実現するものとしての自由競争が基礎づけられる
高島善哉『市民社会論の構想』新評論 1991年 P54
和解
本当の和解というのは、つまるところ人間性の問題だからである。自分自身の人間性を肯定し、他の人びとの人間性を認め、尊重する人間の間でしか成立しえない
デズモンド・ツツ『南アフリカに自由を』サイマル出版会 1983年 P146
笑い
あらゆる笑いは、差別と階級制を内包して生まれる
寺山修司『青蛾館』文藝春秋 1975年
笑いは、硬直状態にたいする反動である
ハンス・リヒター『ダダ』美術出版社 1966年 P102

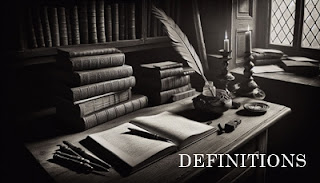.jpeg)